| ●2002年8月の絵日記 |
| 2002年8月27日(火)能登・穴水 輪島へ行ってきました。 残念。カメラを持参しなかったので、写真は撮れず。 去年の日記を見ると、このバケツ田の稲も、9月5日くらいには刈入れ時を迎えたようですから、来週末くらいが新米を神様に差し上げることが出来るかな。 新米の収穫を受けて、いよいよ来月末からは、当社の味噌の仕込みも始まります。 |
| 2002年8月25日(日)バケツ田 だいぶ、稲穂が重くなってきたようだ。 
|
| 2002年8月19日(月)バケツ田 こんな感じです。もう、あんまり水を吸わなくなった。 となりのメダカも、大きくなっている。 写真は、当社の商品ルーム「ひしほ蔵」の入り口に置いたバケツ田と、そのとなりのビオトープの水草の上に動いているタニシの赤ちゃん!
|
| 2002年8月18日(日)お盆も営業しました。 当社工場はお休みしましたが、商品ルーム「ひしほ蔵」はお盆の間も営業しました。 夕方になると、風が涼しい! |
|
2002年8月13日(火) 能登半島( 輪島と穴水 ) 今日は、能登半島の輪島へ商品の配達です。 帰りに、気に入った、日本的な風景を撮りました。 (輪島の近くに広がる田。美しい田園風景。
(穴水町にある、鯔待ち櫓=ボラ待ちやぐら。はるか向こうには、能登島へと続く大橋が見えます。 |
|
2002年8月11日(日) バケツ田と、めだか。 今年も、バケツ田に挑戦。 今は、出穂が済み、花が咲いている。写真では、白い、小さな、それでいて力強い、稲の花が見えるだろうか? 今年は、それにプラスして、,めだかの観察もできるように、工夫して見ました。 さあ、小学校の夏休みの研究がまだの方、ここへ来れば、味噌づくりの工程についての説明一式(要・予約)と、 |
|
2002年8月5日(月) 輸出用の味噌の積み込み
|
| 2002年8月 一週間遅れですが、7月末の大野日吉神社の祭礼の写真を載せます。 祭礼は、日曜日の本祭りをはさんで前後3日間行われています。今日は日曜日の本祭り、神様の巡行・行列のお話です。
幼稚園児による、獅子舞。かわいいね。男の子も、女の子も一日朝から夕方まで、がんばりました。 獅子舞は、幼稚園生・小学生・中学生と、大人による4部編成。舞い方も大人と子供では、その迫力に大きな違いが出ます。 さあ、夕闇迫る頃、参加者は、皆、町内で振舞われたお酒も入って少し気持ち良くなってきた頃。
いよいよクライマックス。日吉神社にお神輿が戻られて、最後に獅子舞の奉納を行って、祭りの行列は終了です。
|
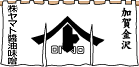 お問合せ:(株)ヤマト醤油味噌 お問合せ:(株)ヤマト醤油味噌〒920-0331 石川県金沢市大野4イ170 TEL.076-268-1248(代) FAX.076-268-1242 e-mail:info@yamato-soysauce-miso.co.jp ▲TOPページへ戻る |









 高校生の山王悪魔払い⇒⇒
高校生の山王悪魔払い⇒⇒






 からくり人形⇒⇒
からくり人形⇒⇒
 ←榊神輿。 本神輿⇒
←榊神輿。 本神輿⇒ ここ、大野町では「エンヤ、エンヤ」という掛け声で神輿は走ります。
ここ、大野町では「エンヤ、エンヤ」という掛け声で神輿は走ります。

 私の好きな、美しい日本の夏の風景がここにあります。
私の好きな、美しい日本の夏の風景がここにあります。



 コレにて全て終了!
コレにて全て終了!